産業医科大学医学部医学科の紹介
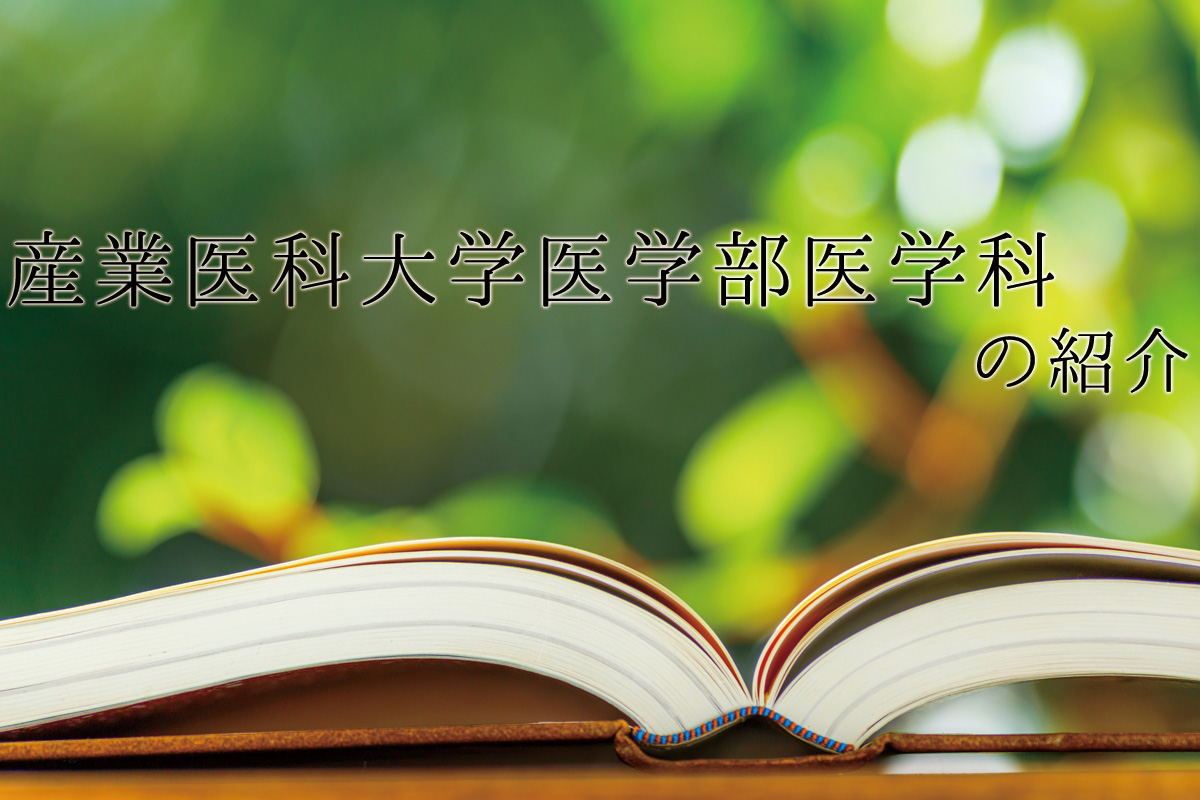
INDEX
産業医科大学医学部医学科概要
産業医科大学医学部医学科は、北九州市に位置する私立医学部です。大学名の通り、産業医の養成に力を入れている点が特徴です。私立医学部ではありますが、産業医科大学の入試では国公立大学のような記述式の設問も多い傾向が見られます。国公立医学部志望生や、論述力に自信のある受験生も産業医科大学医学部受験を検討してみましょう。
産業医科大学医学部募集要項について
アドミッションポリシー
産業医科大学医学部では、産業医育成を目的とした教育が行われることを理解したうえで入学することを求めています。産業医になる意欲はもちろん、健康増進などにも関心を持つ人材が望まれます。また、知識の応用力やコミュニケーション能力、継続的な探求心なども必要です。
学力面では、基礎学力に加えて、語学力の習得も行っておくべきです。医学部受験対策として英語を学ぶ際にも、産業医科大学入学後も役立つ知識だと意識することで、モチベーションを高めてみてください。
カリキュラムポリシー
産業医科大学医学部では、高大の連続性を意識したカリキュラムが設定されます。医学分野の科目のみならず教養科目も重視し、倫理観や優れた人間性などを身につける上で役立てさせる方針です。少人数で行う対話型の授業も多い傾向があり、コミュニケーション能力や協調性を養ううえで役立ちます。
基礎医学教育では、その後の臨床医学教育に役立つ知識や理解が重視されます。臨床医学教育では実際の診療に参加することで、知識・技能の習得や学習意欲の向上に加えて、自ら思考する能力を高めることが可能です。
また、産業医養成を目指す大学らしく、産業医学についての学習は1年次から行われます。実際に産業医として活躍する医師による指導を受けながら現場で実習を実施します。初期の臨床研修に参加する段階で、すでに産業医の資格を取得している状態が可能なカリキュラムが設定されており、産業医科大学医学部の大きな特徴と言えるでしょう。
さらに、着実に知識・理解を積み重ねるために、年次ごとにCBTをはじめとする各種試験が行われます。卒前教育や卒後教育でも産業医学に関する科目が設定されている点や、高校から大学、基礎科目から臨床科目、卒前教育から卒後教育などへの連続性が重視されている点も特徴的です。
ディプロマポリシー
産業医科大学医学部では、医師になるうえで必要な各種試験への合格や、必要科目の履修に加えて、産業医として活躍する能力を備えて卒業することを求めています。
産業医に必要な知識・技能・人間性を養い、産業医分野で主体的に活躍する意欲を持つことが必要です。
住所、定員、偏差値などの基本情報
| 住所 | 北九州市八幡西区医生ヶ丘1番1号 |
|---|---|
| アクセス | JR鹿児島本線「折尾」駅からバス約10分「産業医科大学病院」または「産業医科大学病院入口」停下車 |
| 定員 | <令和4年度>学校推薦型選抜25名以内、一般選抜約80名 |
| 設置時期 | 1978年(昭和53年)1月 |
| 偏差値 | 67.5(2021年度入試医学部ボーダー偏差値、河合塾) |
科目ごとの傾向
英語
英語では、分量がやや多めの記述式問題が出題される傾向があります。日本語での内容説明や英文和訳、自由英作文などの対策を行っておきましょう。産業医科大学は私立医学部ですが、国立医学部の2次試験のような記述問題が多く、記号問題は少ないです。
読解問題では、空所補充形式の問題に特徴があります。選択肢から選ぶのではなく、自ら単語を書く必要があるため、単語学習の際はつづりも正確に覚えておく必要があります。
自由英作文では100語程度の英語を書く必要があります。論理的な英文構成の練習はもちろん、制限時間を意識してテキパキと書く内容を整理する対策もしておきましょう。産業医科大学医学部の英語では、近年注目度が高まっているテーマに関する出題も少なくありません。
例えば、2020年度は昆虫食に関する英文読解、2021年度はレジ袋有料化に関する自由英作文が出題されました。小論文対策も兼ねて、時事ニュースなどにも興味を持っておくと良いでしょう。
数学
数学では、小問形式の出題が多い傾向があります。そのため、特定分野の力を磨き上げるよりも、幅広い分野の問題をきっちり解く力を身につけておくと有効です。
産業医科大学医学部では数学Ⅲも出題範囲に含まれており、微積分などで計算量が多い問題も見られます。計算力をつけると同時に、より効率よく計算することができないかを常に意識しておいてください。加えて、多くの小問の中から手早く解けそうな問題を見つけ出す力も大切です。
また、2021年度大問1では有効数字に関する計算が登場しました。単位の変換作業などで計算ミスが出やすい問題で、正確な計算力を磨く対策も重要と言えます。
また、記述式の問題で、証明問題が出されることもあります。証明問題では論理を特に明確に示す必要があるため、過去問演習では、答案の添削指導を受けるなどして論理的な記述をする対策を意識してください。
化学
化学では、有機や理論分野の出題が多く見られます。難易度は標準的なので、頻出分野を中心に問題集や過去問などで基礎~標準レベルの問題演習を重ねておきましょう。
計算問題や論述問題も出題されます。計算問題の難易度も標準的な傾向ですが、産業医科大学医学部の理科は2科目で100分と制限時間に余裕が少ないです。そのため、解き方をマスターしておくことに加えて、素早く正確に計算を進める対策をしておきましょう。
論述問題も極端に恐れることはなく、過去問演習で形式に慣れておき、極端に苦手な分野がある場合は教科書の見直しなどで知識・理解を補っておいてください。
生物
生物では、遺伝や生殖など、医学部での学習に特に深くかかわる分野からの出題が多く見られます。論述問題が含まれることも考えると時間の余裕は少なく、テキパキ解き進めると同時に、解ける問題での失点を避ける対策が重要です。
論述問題では、実験の過程説明が求められるケースもあります。教科書などで実験が登場した際は、目的・結果のみならず、実験過程についてもしっかり理解しておきましょう。
2021年度入試でも大問1・大問3で論述問題が出されており、産業医科大学医学部の生物では論述力が重視される傾向があります。過去問演習を通じて、論述対策も十分に行っておいてください。
物理
物理では、標準レベルの問題が多い傾向があります。2科目で100分という制限時間に対して設問数が多く、テキパキと解き進める対策が重要です。過去問演習では、問題を解く順序を工夫して、効率よく得点を重ねる対策を行っておきましょう。
力学の出題頻度が高い傾向はありますが、2019年度は原子からの出題がありました。
また、2021年度はマークシート方式の記号問題も登場しています。そのため、産業医科大学物理の過去問演習では、複数年度の問題にチャレンジし、前年に出題されていない分野や形式への対策も怠らないようにしましょう。
計算問題を素早く解き進めることが得点アップにつながるため、制限時間を設定して問題集などに取り組む学習も取り入れてみてください。





この投稿へのトラックバック
トラックバックはありません。